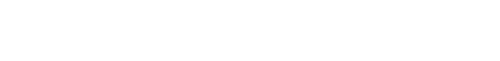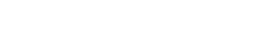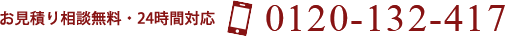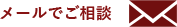プライバシーについて
探偵・興信所の仕事は依頼者から依頼を受けて「ある人物の情報や行動」を調べることが多く、それが個人情報やプライバシーの問題にかかわってくると思われます。
興信所に調べられたくないというお気持ちはもちろん理解しております。(※探偵である著者の私自身も他人から調べられたくなどないと思います。)
探偵の調査が「個人情報保護法違反だ」とか「プライバシーの侵害だ」というご意見を耳にすることもあります。
但しこれは少々異なると考えております。その理由の一つは、基本的に人の何らかを調べたということで、個人情報保護法その他の法律違反となるわけではないからです。
探偵・興信所と個人情報保護法
例えば個人情報保護法という法律は、顧客などの個人情報を大量(5000件以上)保有している企業の情報管理を対象とした法律となります。
※2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行され「5000件以上」の要件は撤廃されました。
同法のポイントは以下となります。
保護が必要な3種類の情報
1.個人情報
●生存する特定の個人を識別できる情報
・個人識別符号が含まれるもの
・他の情報と容易に照合でき、その結果、特定個人を識別できる情報を含む
例)免許証番号、指紋認証データ等●要配慮個人情報
・本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯歴、犯罪被害の事実2.個人データ
1のうち、紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの(個人情報データベース等)に含まれる個人情報
3.保有個人データ
2のうち、開示、訂正、消去等の権限を有し、かつ6か月を超えて保有するもの
同法の義務を負う者は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」です。
この個人情報データベース等とはメールのアドレス帳なども含まれ、通常は「顧客などサービス利用者」の情報データベースが該当します(他に従業員など)。

探偵・興信所とプライバシー
では、プライバシーの侵害についてはどうでしょうか。
法律上のプライバシー侵害とは、本来誰にも見られずにすむ場所、例えば自室の中や風呂場、トイレ等での侵害行為(いわゆる覗き等)を指します。
もちろん探偵は部屋や風呂場を覗くことを仕事としているわけではありませんし、街中や店内、道路など誰にでも見られてしまう場所では個人のプライバシーは存在していないと考えられるのです。
人は誰かに調べられる
そもそも「誰かに調べられる」ということ自体を、世の中で生きている限りは避けることはできないのではないでしょうか。
例え調べたのが探偵や興信所であっても、調べようと思う人は別の人であり、それぞれが調べたい、または調べなければならない理由を持っているからです。
少し分かりやすい例を挙げると「採用調査」というものがあります。
誰でも企業で働こうとする際にわざわざ自分のことを色々と調べられたくはないとは思いますが、素行の悪い人間、横領を働く人間、場合によっては産業スパイなど多大な不利益をもたらす人物が入り込む可能性があります。
企業の立場から考えると、どこの馬の骨ともわからない人間を簡単に採用するわけにはいきませんので事前に調査が必要になってくるわけです。
これは一つの例として挙げたまでであり、その他さまざまなケースに置き換えることができます。
探偵が人を調べようが調べまいが、人は人生のどこかで調べられる機会は訪れます。
企業には企業の事情がありますし、人には自分の人生がありますので、そのために他者を調べることが必要になることもあるでしょう。
調べられたくないと思っても、調査をする探偵や興信所がなくなったとしても、おそらくその事実は変わらないであろうと思います。
興信所の経験からあえて言えることがあるとすれば、できるだけ「品行方正」に生きていれば誰かに調べられる機会は減るのではないでしょうか。
逆に、例えば「すぐに浮気してしまうような人」は、他の人よりも調べられる機会が多いかもしれません。